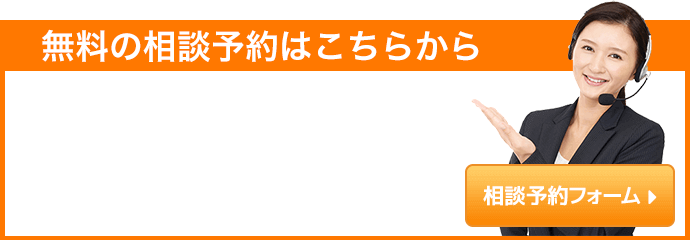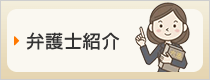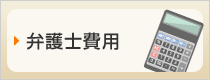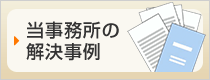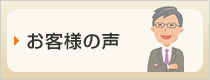遺言の有効・無効性の争い
1 遺言が争われるケース
遺言が争われる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定していなかったような遺言が出てくる場合があります。
全ての財産を〇〇に相続させるという遺言が出てきたら
Aさんの父(Bさん)は、晩年、寝たきり状態となり、病院に5年間ほど入院していましたが、ある年、病院で亡くなりました。
AさんがBさんのお通夜に参列すると、そこには、AさんにもBさんにも20年以上顔を見せていなかったAさんの兄Cさんが来ていました。Cさんは、お通夜の席で、Aさんに対し、「実は父さんに遺言を書いてもらっている」と言って、遺言書を渡してきました。渡された遺言書を見ると、そこには、「財産は全てCに相続させる」と書かれていました。
AさんがBさんのお通夜に参列すると、そこには、AさんにもBさんにも20年以上顔を見せていなかったAさんの兄Cさんが来ていました。Cさんは、お通夜の席で、Aさんに対し、「実は父さんに遺言を書いてもらっている」と言って、遺言書を渡してきました。渡された遺言書を見ると、そこには、「財産は全てCに相続させる」と書かれていました。
あなたがAさんの立場だったら、どうされますか?
遺言が争われる場面では、このようなケースが多くあります。そこで、このような場合、Aさんとしてはどのような対応をとることができるかについて、ご説明します。
遺言が争われる場面では、このようなケースが多くあります。そこで、このような場合、Aさんとしてはどのような対応をとることができるかについて、ご説明します。
遺言の無効主張
想定外の遺言が出てきた場合、その遺言が無効であると主張することが考えられます。その主張の内容は、遺言の種類に応じて異なります。
⑴ 自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、押印することで作成することができる遺言です。
この自筆証書遺言は、遺言の中でも最も簡単に作ることができ、それだけに最もよく使われる遺言でもあります。しかし、作成が簡単な一方、紛失・偽造・変造の危険があったり、内容が不明確だったりという理由で、遺言の有効性が争われやすい遺言でもあります。
このような自筆証書遺言では、次のような観点から遺言が無効であると主張することが考えられます。
ア 遺言の法律上の方式に反している
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、押印する必要があるなど一定の法律上の方式があります。このような方式を順守していないと、それを理由に遺言が無効とされることがあります。
たとえば、パソコンで遺言を作成・印刷し、そこに署名・押印したとしても、これは全文が自筆されていないことになるので、無効となります(もっとも、平成30年の相続法改正により、財産目録についてはパソコンで作成し、各頁に署名・押印すれば足りることとされました。)。
また、遺言を作成する際、自分一人では手が震えて書くことができないため、誰かに手を取ってもらって書くという場合もありますが、このような方法によって作成された自筆証書遺言についても、無効となる場合があります。
したがって、遺言が上記のような形式的要件を満たしていなければ、これを理由に遺言が無効であると主張することが考えられます。
弁護士に依頼した場合、弁護士が、遺言の方式を順守しているか検討し、遺言の有効性を判断します。逆に、これから遺言を作成するという段階の場合は、弁護士が、遺言の方式を順守できているかチェックしますので、後で無効とされるリスクを減らすことができます。
イ 遺言能力がなかった
遺言能力とは、遺言を有効にすることができる能力をいいます。
原則として、15歳に達した者であれば遺言能力があります(民法961条)。
しかし、自分の遺言の意味(誰に何の財産を与えるのかなど)を理解することができないような場合、遺言能力が否定され、遺言は無効となります。
原則として、15歳に達した者であれば遺言能力があります(民法961条)。
しかし、自分の遺言の意味(誰に何の財産を与えるのかなど)を理解することができないような場合、遺言能力が否定され、遺言は無効となります。
たとえば、亡くなった方(被相続人)が、遺言作成当時、認知症などの理由で遺言の意味を理解していたか疑わしいような事情がある場合、遺言能力がなかったため遺言は無効であると主張することが考えられます。
実際に遺言能力が否定されるか否かは、様々な事情を考慮した上での法律的な判断になるため、生前に認知症だと診断されていても遺言能力が認められる場合もありますし、逆に認知症と診断されていなくても遺言能力が認められない場合もあります。
弁護士に依頼した場合、弁護士が、医師による診断(カルテの分析)だけなく、被相続人の生前の様子、遺言の内容等の様々な事情を収集・分析し、遺言能力の有無を争うことができるかを判断します。
ウ 偽造されている
遺言が偽造、すなわち遺言者以外の他人によって作成されたものであると主張する場合もあります。
たとえば、出てきた遺言書の文字が被相続人の他の文書の文字と異なる場合や、生前疎遠だった親戚に全て相続させる等遺言の内容が不自然である場合に、遺言の偽造が考えられます。
遺言が偽造か否かについては、筆跡鑑定をすればよいと思われるかもしれませんが、裁判では必ずしも筆跡鑑定の結果のみで決まるわけではなく、遺言の内容等の様々な事情を考慮した上で、偽造の有無が判断されます。
弁護士に依頼した場合、弁護士が、筆跡や遺言の内容等の事情を収集・分析し、偽造遺言と判断される見込みがあるか否かを判断します。
⑵ 公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは、公証人が、適法かつ有効に遺言がなされたことを証明する公正証書という文書によってなされる遺言です。
公正証書遺言は、証人2人の立会いの下、公証人の面前で、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人がその内容を文書にまとめ、遺言とするものです。
公正証書遺言は、証人2人の立会いの下、公証人の面前で、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人がその内容を文書にまとめ、遺言とするものです。
このように作成された公正証書遺言は、公証人が介在することから、自筆証書遺言に比して、遺言が無効とされるリスクは小さくなります。しかし、次のような場合は、公正証書遺言であっても無効とされる可能性があります。
ア 遺言能力が否定される場合
自筆証書遺言と同様、遺言者が、遺言する時に、遺言の意味を理解できる能力がなかった場合、公正証書遺言は無効となります。
もちろん、公証人は、遺言者が、遺言の意味を理解できているか確かめながら遺言を作成するため、自筆証書遺言に比べ、遺言時に遺言能力がなかったと判断されることは多くありません。しかし、公証人の確認が不十分であった場合等は、遺言能力がなかったと判断される場合もあり得ます。
弁護士に依頼した場合、弁護士は、公正証書遺言を作った時、遺言者が遺言の意味を理解できる状態だったのか、公証人はどのようにして遺言者の遺言能力を確かめたのか、公証人のした確認は十分といえるのかを調査し、公正証書遺言が無効とされる見込みの有無を判断します。
イ 口授が行われなかった場合
口授とは、遺言者が、公証人に対し、遺言の内容を口で伝えることをいいます。
このような口授が、実際には遺言者が頷いていただけであったり、「はい」という返事をしていただけであったりといった場合は、適法な口授がなかったものとして、公正証書遺言が無効とされる可能性があります。
このような口授が、実際には遺言者が頷いていただけであったり、「はい」という返事をしていただけであったりといった場合は、適法な口授がなかったものとして、公正証書遺言が無効とされる可能性があります。
弁護士に依頼した場合は、適法な口授がなされたかを調査し、公正証書遺言が無効とされる見込みがあるかを判断します。
3 遺言の有効性が認められてしまったら
(具体例)
AさんにはB、Cという子供がいました(Aさんの配偶者は既に亡くなっています)。Aさんが亡くなり、「全財産をCに相続させる」という遺言が見つかりました。Bさんは、遺言の有効性について検討したものの、遺言が無効とされる見込みは低いことがわかりました。
このような場合、Bさんは、財産を相続することができないのでしょうか。民法は、兄弟姉妹以外の相続人に、どのような遺言がされたとしても最低限もらえる取り分として「遺留分」を認めています。遺留分の額は、原則として法律上もらえるはずの相続分の半分となります。*
たとえば、上記の具体例でAさんの財産が8000万円だったとすると、Bさんが法律上もらえるはずの相続分は1/2なので、その半分の1/4にあたる2000万円が遺留分となります。したがって、遺言の内容がどのようなものであっても、Aさんは、最低でも2000万円については相続できることとなります(ただし、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内又は相続開始から10年以内に権利を行使する必要があります。)。
弁護士に依頼した場合、弁護士が、まず遺言の有効性を争うことができないか検討します。その上で、遺言が無効であると主張することが難しい場合は、遺留分を計算し、最低でも遺留分について相続したこと(遺言が遺留分を侵害していること)を主張します。
*相続される方が直系尊属(亡くなった方の父母やそれより上の親族)のみの場合は、本来もらえる相続分の1/3となります。
4 主張方法
では、遺言が無効である可能性がある場合、どのようにして遺言無効を主張するのでしょうか。もちろん、話し合いによる遺産分割協議ということも考えられますが、話し合いでまとまらない場合には、法的な手続として遺産分割調停と民事訴訟が考えられます。
⑴ 遺産分割調停
まずは、遺産分割調停を申し立て、調停手続の中で遺言が無効であることを主張します。調停とは、裁判所が介入して行う話し合いです。
もっとも、遺言の有効性は、本来的には訴訟でなければ判断できない事項とされています。そのため、当事者全員で有効性について合意できれば調停でもよいのですが、この点について合意できない場合には、⑵の民事訴訟を提起せざるを得ません。
⑵ 民事訴訟
遺産分割調停によっても解決に至らなかった場合、訴訟となります。具体的には、まさに遺言が無効か否かについて判決をもらう、遺言無効確認請求訴訟を提起することとなります。
⑶ 弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、その中での主張や立証、和解交渉等を行います。
これらの調停や訴訟の手続は、ご本人で行うこともできますが、専門的な知識や戦略性が要求されますし、手続が煩雑であったり、言いたいことがうまく裁判官に伝わらなかったりするおそれがあります。弁護士であれば、依頼者のお話をよく聞いた上で、その内容を書面にまとめ、効果的に裁判官に伝えることが可能です。